今までは自動運転システム自体の研究開発が中心でしたが、1990年代に入ると「どうやって自動運転システムを現実の道路に出せるのか」という段階へと進みました。
各地域で大規模なITS(高度道路交通システム)プロジェクトが立ち上げられ、交通効率や安全性の向上を目指した取り組みが行われました。
ヨーロッパ:Eureka PROMETHEUS Project(ユーレカ・プロメテウス計画)
1986年、欧州先端技術共同体構想(EUREKA)にて大規模なITSプロジェクト「PROMETHEUS(プロメテウス」が発足しました。
このプロジェクトは交通効率と安全性の向上を目的とした大規模な無人自動車の研究開発プロジェクトで、複数の大学や研究機関、ヨーロッパの主要自動車メーカーを中心とした600社もの企業などが参加、EUREKA加盟国からは7億4,900万ユーロの資金提供を受けたという大規模な研究開発プロジェクトでした。
プロジェクトを策定するにあたり、40以上の研究機関と協力して、7つのサブプロジェクトからなるプログラムが作成され、運営委員会の下には以下の産業研究に関する3つのプロジェクトと基礎研究に関する4つのプロジェクトが出来ました。
【産業研究】
- PRO-CAR:コンピュータシステムによる運転支援
- PRO-NET: 車車間通信
- PRO-ROAD: 車両と環境間のコミュニケーション
【基礎研究】
- PRO-ART : 人工知能の方法とシステム
- PRO-CHIP: 車両内のインテリジェント処理のためのカスタムハードウェア
- PRO-COM: コミュニケーションの方法と標準
- PRO-GEN: 新しい評価と新しいシステムの導入のための交通シナリオ
プロメテウス計画で特筆すべき車は、”VaMP “と”VITA II”の2台ですね。
この車は3代目のメルセデス・ベンツ・Sクラスをベースに、ミュンヘン連邦国防大学とダイムラー・ベンツ(現メルセデス・ベンツ)が共同で開発しました。
搭載されていたシステムは、ミュンヘン連邦国防大学が開発した”VaMoRs”をベースに小型化・改良されたマシンビジョンシステムです。
1994年にはVaMPとVITA Ⅱがパリにある複線の高速道路を最高で130 km/h以上の速度で走行、交通量が多い状況でありながらも、1,000km以上走行することに成功。
また、他車両が通行していない道路での自立走行、隊列走行、他車両への自動追従、他車両の自立的追い越し運転において車線変更を行うなどの実地検証を行いました。
1995年にはVaMPがバイエルン州ミュンヘンからデンマークのオーデンセまでの往復1000マイルを走破。ドイツのアウトバーン上で175 km/h以上の速度を出すことが出来ました。
プロメテウス計画は後に以下のテーマを一般公開し、数多くの自動運転に関する業績の基礎となりました。
- CED 1: 視力強化
- CED 2-1 : 摩擦モニタリングと車両ダイナミクス
- CED 2-2 : 車線維持サポート
- CED 2-3: 視程範囲の監視
- CED 2-4: ドライバーステータスモニタリング
- CED 3: 衝突回避
- CED 4: 協調運転
- CED 5: 自律型インテリジェントクルーズコントロール
- CED 6 : 自動緊急通報
- CED 7: フリート管理
- CED 9: デュアルモードルートガイダンス
- CED 10: トリップおよび交通情報システム
…ちなみに8番目のCED 8 (テスト フィールド) が抜けている理理由は、資金調達の構造とスケジュールに合わないことが判明したため、中止されたみたいです。

…ちなみに8番目のCED 8 (テスト フィールド) が抜けている理理由は、資金調達の構造とスケジュールに合わないことが判明したため、中止されたみたいです。
アメリカ:AHS(自動道路システム)計画
1980年代後半、アメリカでは交通事故と深刻な渋滞が社会問題となっていました。
そこで、自動運転技術をITSに取り込み、解決を図ろうという動きが出てきます。
1991年、米国議会はISTEA(Intermodal Surface Transportation Efficiency Act:総合陸上交通効率化法)が制定、連邦政府からの助成金予算は総額1533億ドルで、そのうち6.6憶ドルがITS技術分野に出資されました。
1994年、政府と民間企業の連携によってNAHSC(National Automated Highway System Consortium:米国自動走行道路コンソーシアム)が結成、
そして1997年には技術的に自動運転が実現可能なのかを示すことを目的に、カリフォルニア州サンディエゴ近郊ののインターステートハイウェイ15号線にあるHOVレーン内で大規模な実証実験「Demo ’97」が実施されました。
Demo ’97では8月7日から11日にかけて、以下7つのチームが自動運転のデモンストレーションを行いました。
- カリフォルニアPATH:磁気マーカーによる路車協調方式を採用。8台の車両が車間距離6.3m、時速96kmで隊列走行を実施。目的は車間距離を短くすることで渋滞を防ぐこと。
- カーネギーメロン大学:乗用車2台、ミニバン1台、バス2台をマシンビジョンによる自動運転で走行。目的は混在交通下での自動運転の実現。
- オハイオ州立大学:マシンビジョンと道路に貼り付けたレーダー反射テープを組み合わせ、2台の乗用車が追い越しを含むシナリオで自動運転を実施。衝突防止用のレーダーを自動運転用のセンサーとして利用していて、これが路車協調方式の”鶏と卵”問題に対する1つの答えになりました。
- トヨタ自動車:運転支援技術「アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC)」を搭載した車両を走行。これを発展させていくことで自動運転を実現させていく方針を示しました。
- 本田技研工業:マシンビジョンによる方式と、PATHが設置した磁気マーカー方式の両方を採用。前者は道路側設備が貧弱な僻地向け、後者は道路側設備が整備されてる都市部などへの対応を意識しています。
- イートン・ボラド社:大型トラック向けACCのデモ走行を実施。先頭車両にはレーダーの反射を抑えるFRP製ボディを採用したスポーツカーを使用していました。
- カリフォルニア運輸省:磁気マーカーのメンテナンス用にマシンビジョンによる自動運転を走行。
日本:AHS(自動道路システム)
日本でも同様のITSプロジェクトが始まります。
1995年3月20日、地下鉄サリン事件のあったその日、建設省(現・国土交通省)は自動車メーカー各社を集め、こんな感じの事を言いました。
- 10月に道路に打ち込んだ”磁気釘”を読み取る路車協調方式の自動運転システムの実験やるから車作って
- 磁気センサーはトヨタさんから買ってね
- 実験車は2台以上作ってね
- 実験車の製作費は自腹でお願い
- 実験には海外の要人を招待して車に乗ってもらうからそのつもりでがんばってね
要するに、すでに予算や人員配置等の計画が決まった後に、1年くらいかかるところを半年以内で事故を起こさない自動運転システムを開発しろってことですね。

それも自腹を切ってです。
ですが、日本の自動車メーカーは見事にこれを実現します。
1995年10月にはつくば市の土木研究所のテストコースで、1996年には上信越自動車道・小諸IC付近でのデモ走行が行われました。
この開発スピードの速さには、アメリカの来客が驚いたと言われています。
自分たちが5年以上かけてやろうとしてた事を、1年くらいでやられたらびっくりしますよね。
ちなみに、このプロジェクトが始まったきっかけはアメリカのAHS計画がきっかけとなり始まったみたいです。
1995年、当時の建設大臣が訪米したとき、2年後にAHS計画のデモンストレーションを行う予定があるという話を聞いたみたいで、帰国してから建設省官僚に…
「日本では自動走行はどうなったいるのか?」
って質問をしました。
ここまでなら別にキッカケでも何でもないのですが…質問された官僚さんがどういう訳か、
「今すぐ自動運転を開発してデモンストレーションをしなきゃ!!!」
…と拡大解釈してしまったのが、このプロジェクトを始めるきっかけとなったみたいです。
ちょっと笑えますが、自動車メーカーの人たちはたまったものじゃないですね。
成功はしたけれど…
日本、アメリカ、ヨーロッパ、それぞれで行われたITSプロジェクトは、技術的には一定の成功を収めました。
しかし、実際に社会に導入するとなると、いくつかの課題が浮き彫りになります。
- 自動運転専用インフラの整備に膨大なコストがかかる
- 一般車との混在交通では、かえって事故のリスクが高まる可能性がある
こうした懸念から、各国のプロジェクトは凍結、あるいは大幅な縮小へと舵を切ることになりました。
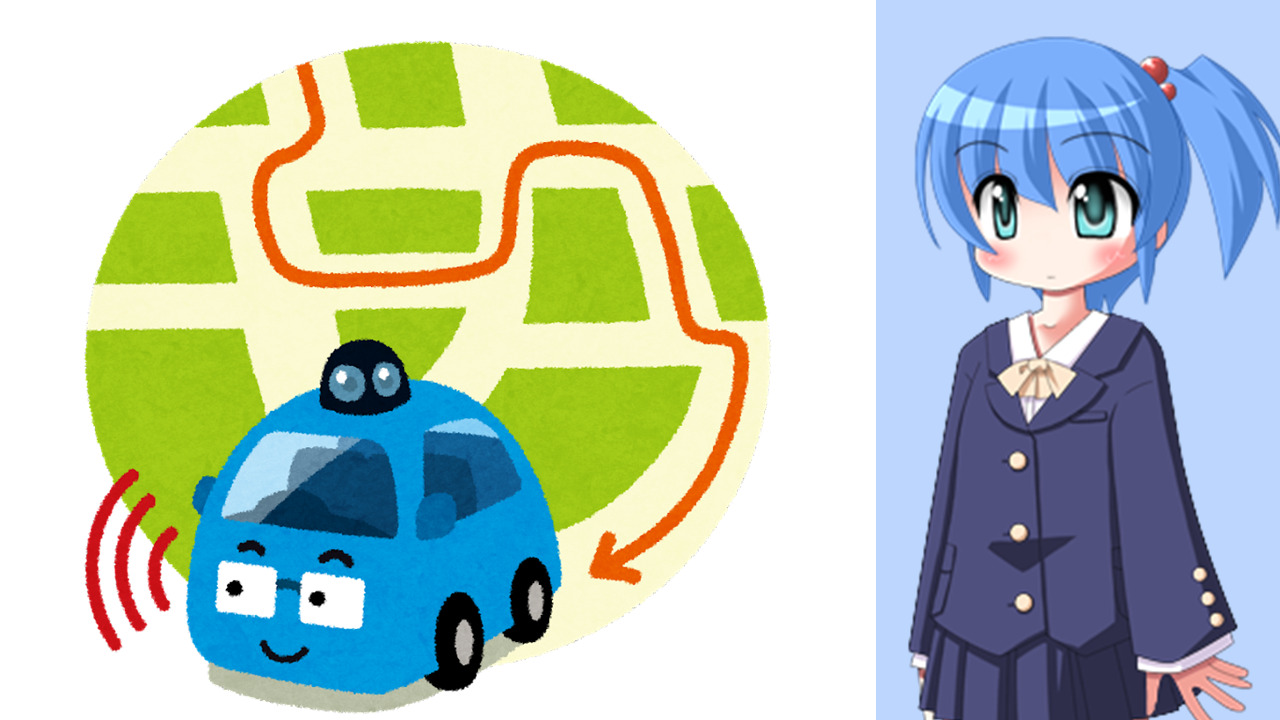


コメント