1970年代、マシンビジョンの登場や第2次AIブームの到来など、コンピュータ技術が急速に進化しており、自動運転の研究にも追い風となっていました。
その結果、道路にケーブルを埋める必要のない自動運転システムが登場しました。
スタンフォード・カート
1961年、アメリカ・スタンフォード大学は、スタンフォード・カートという月面探査機のプロトタイプを作りました。
この車両は人間が遠隔操作するために作られ、テレビカメラと無線通信機のみを搭載していました。
月面探査という本来の目的は果たせなかったものの、後の研究者たちによって自動運転の研究用車両として改造され、
- 1971年には白線をカメラで読み取って走行するシステムが搭載
- 1977年には2眼式のカメラを搭載して立体視に対応
- 1979年には障害物をよける機能が搭載
と、徐々に自動運転機能を獲得していきました。
シェーキー
スタンフォード研究所(現・SRIインターナショナル)の人工知能センターでは、1966年から1972年にかけてシェーキー(Shakey)と呼ばれるロボットを開発しました。
このロボットの高さは約2メートルほどで、無線リンク用アンテナ、ソナー距離計、テレビカメラ、オンボードプロセッサ、衝突検出センサーなどを搭載しています。
そしてコンピュータビジョン、自然言語処理、論理推論などの技術を組み合わせ、移動が可能な世界初の汎用ロボットとして行動を決定できる点が大きな特徴でした。
シェーキーで開発された技術は、現在、以下のような分野に応用されています。
- Siriのような自然言語対話
- 自動車の車線逸脱防止支援システム
- A*(エースター)探索アルゴリズムによる経路探索(カーナビ等に応用)
- NASAの火星探査機ローバーの自律ナビゲーション

ちなみに名前の由来は「めっちゃ揺れるから」だそうです。
知能自動車
1977年、日本の通商産業省(現・経済産業省)機械技術研究所は、世界で初めて自律方式を採用した自動運転車「知能自動車」を開発しました。
この車両には2台のカメラが搭載され、視差を利用して障害物を検出。道路下のレールや磁気センサーに頼ることなく、周囲の環境を視覚的に捉えて走行するという、のちにマシンビジョン技術の原型となる方式が用いられていました。
ALV
1980年代、アメリカではDARPA(国防高等研究計画局)が無人偵察を目的とした自動運転車の開発計画が立ち上がり、メリーランド大学やマーチンマリエッタ社によってALV(Autonomous Land Vehicle)が開発されました。
外観は高さ約3m、全長約4.1mの白色に青いラインの入った四角い8輪の車両で、ルーフにカメラとセンサーが取り付けられ、無人で自動運転しました。
一応1987 年 11 月までに重要なマイルストーンを達成したのですが、1988年にプロジェクトは中止されました。
理由は軍関係者がイマイチ開発目的を理解してなかったからだそうです。
まぁ、デカくて遅くて目立つ上に、3つのディーゼルエンジンを轟かせてたら偵察は無理っぽいと思われて仕方ないのかもしれません。
NavLabとALVINN
ALVの成果は、カーネギーメロン大学(CMU)のNavLabプロジェクトに引き継がれました。
Navlab は、カーネギーメロン大学コンピュータサイエンス学部のロボット研究所チームによって開発された、一連の自律型および半自律型の自動運転車で、Navlab1からNavlab11まで製造されました。
1984年にコンピュータ制御車両の研究を開始し、最初の車両である Navlab1の生産は1986年に始まりました。
Navlabシリーズの車両は、「オフロード偵察」「高速道路の自動化」「オフロード衝突防止」「混雑した都市環境での操縦補助」といった幅広い目的に対応するよう設計されており、車種のラインナップも「ロボットカー、バン、SUV、バス」など多岐にわたっていました。
ほとんどの車両は半自律型ですが、中には完全自律走行を実現し、人間の介入を不要とするものも存在しました。
また、1988年にはALVINNが開発されました。
ALVINNという名前はAutonomous Land Vehicle In a Neural Networkの頭文字からつけられていて、その特徴はセンサーデータと映像をもとに、人間の運転を模倣する形でステアリング操作を学習する能力があることです。
つまり、ニューラルネットワークを使った世界初の自動運転車ということになります。
VaMoRs
ドイツでは1980年代半ばから、ミュンヘン連邦国防大学で自律走行車の研究が行われ、VaMoRsという車を開発しました。
VaMoRsはメルセデス・ベンツ製のバンをベースにマシンビジョンを活用した自動運転車で、閉鎖されたアウトバーンを約88km/hを達成しました。
この実験では安全対策としてエンジニアが運転席に座っていたものの、実際の走行操作はすべてシステムが行っていたとのことです。
<参考文献・リンク>
【書籍】
- 保坂明夫,青木啓二,津川定之:自動運転(第2版)―システム構成と要素技術―,森北出版,(2019)
- 古川 修:自動運転の技術開発 その歴史と実用化への方向性,グランプリ出版,(2019)
【ウェブサイト】
- “自動運転の歴史と現状(2023年最新版)”. 自動運転ラボ,(‘2023年3月1日閲覧)
- “自動運転車の歴史 1920年代から現在まで 前編”. AUTOCAR JAPAN. ,(‘2025年3月1日閲覧)
- 津川 定之,”自動運転システムの60年,2015 年 54 巻 11 号 p. 797-802,(‘2025年3月1日閲覧)
【Wikipedia】
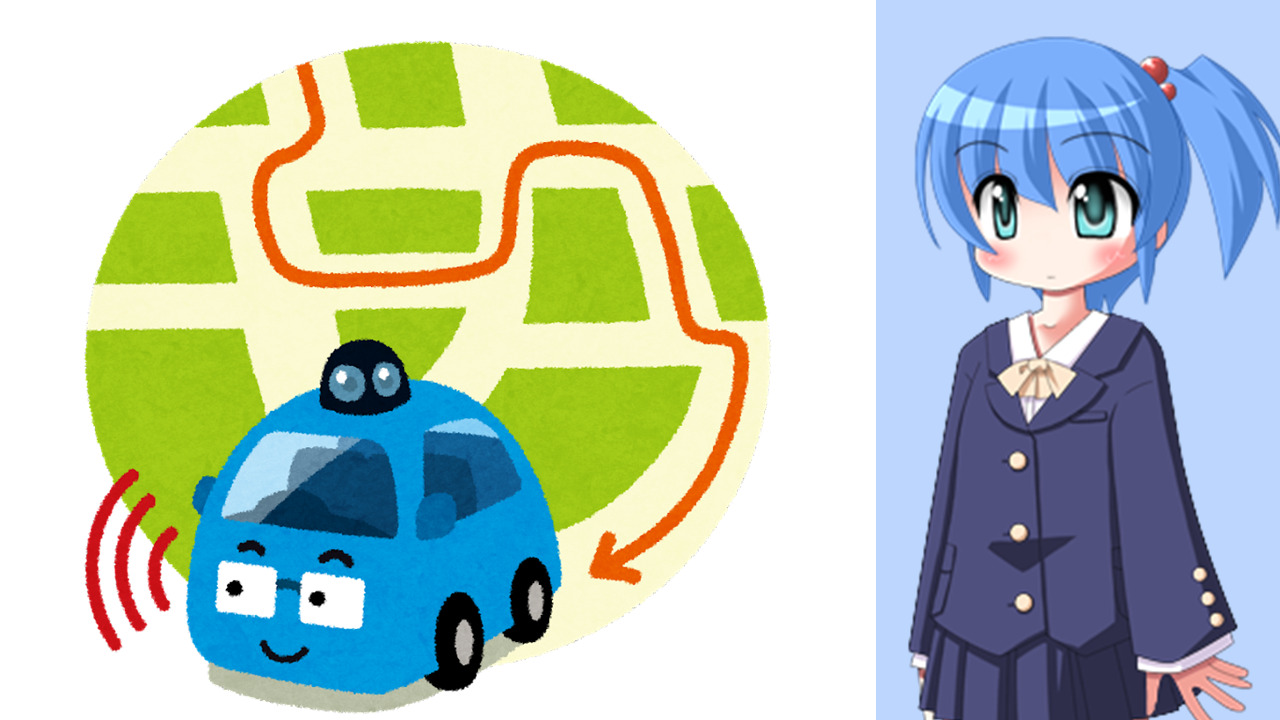

コメント